薬局のバックヤードでこぼした、誰にも見せられないため息
白衣を脱ぎ、時計に目をやると、もう閉店時間。薬局の奥、バックヤードの隅っこで、ふぅ、とため息をついた。誰にも聞かれないように、気配を消すように。患者さんの前ではいつも明るく、穏やかに対応していたつもりだけど、内心ではずっと緊張していた。
人手不足の中で新しいスタッフの指導も任され、年度始めの忙しさと重なって、肩にのしかかる責任がどんどん重くなる。
「これくらい自分で何とかしないと」
そう思っていたのに、気づけば心も体もギリギリだった。
頼ることが苦手だ。迷惑をかけたくない。弱いと思われたくない。
だけどそんなふうに全部抱えていると、ある瞬間ふと、自分がとても“弱い存在”に思えてくる。
そして心のどこかで、問いが浮かぶ。
「自分は本当に、このままでいいんだろうか?」
結論:弱さは“考える力”と矛盾しない
私たちのモヤモヤの正体は、「弱さ=ダメなこと」という思い込みだ。
「考える葦」――壊れやすさの中に、尊さがある
フランスの思想家パスカルは、こう語った。
「人間は考える葦である。」
風に揺れる細い葦(あし)のように、人間は自然界でもっとも壊れやすい存在だ。病気にもなるし、感情にも揺さぶられる。でも人間には、唯一「考える力」がある。
その力によって、自分自身や世界に意味を見出し、どんな困難も乗り越えられる――そうパスカルは言う。
「弱さ」と「思考力」は、矛盾しない。むしろ、弱いからこそ考えるのだ。
30歳の春、心が折れそうになった日
それを痛感したのは、ちょうど今年の春だった。
新年度が始まり、職場に新しいスタッフが加わった。指導やフォローに加え、処方箋の件数も増え、気づけば毎日が目まぐるしい。
患者さんには笑顔で対応しながらも、心のなかでは「もっと効率的に動けたら…」「また失敗したらどうしよう」と、自分を責める声が止まらなかった。
夜遅く家に帰り、スマホをぼんやり眺めていたある日、不意に目に入ったパスカルの言葉。
「人間は考える葦である」
それを読んだ瞬間、涙が出そうになった。
ああ、自分は弱くてもいいんだ。
しんどい日々の中で、それでも考えていた。「どうしたらうまくいくだろう」「何が正解だったんだろう」――その姿勢こそが、私たちの尊さなのだと。
「強くあらねば」と無理にふるまうより、壊れそうでも考え続けている自分に、少し誇りを持ってもいいのかもしれない。
そう思えたとき、肩の力がすっと抜けた。
今日からできる「考える葦ワーク」3選
①「弱さメモ」をつける
ノートやスマホのメモ帳に、日々感じた「自分の弱さ」を正直に書いてみる。「今日は患者さんにきつく言われて、心が折れた」「指導のとき、うまく言えなくて自信を失った」――そんな小さな記録でいい。
そして最後にひと言、「それでも私は考えている」と添えてみよう。
弱さを認めたその瞬間こそ、考える力が働いている証なのだから。
②哲学的ひとりごと時間をつくる
一日の終わり、寝る前に5分間、スマホを閉じて、ぼーっと考える時間をつくってみる。テーマは「私はなぜ、今日も頑張ったんだろう?」でも「人はなぜ迷うのか?」でも、なんでもいい。
考えることに正解はない。だけど、自分に問いかけるその行為そのものが、「考える葦」としての営みなのだ。
③誰かの“弱さ”に寄り添ってみる
自分の弱さを受け入れるのが難しいときは、まず他人の弱さに目を向けてみよう。
同僚の疲れた表情、患者さんの沈黙。その一瞬に気づいて「大丈夫?」と声をかけるだけでいい。
他人の弱さを受け止める目線を持つことで、自分にもそのまなざしを向けられるようになる。不思議と、心がふっと温かくなるはずだ。
「壊れやすくても、私は私」を胸に歩こう
私たちは、決して“完璧な強さ”を持って生きていけるわけじゃない。
むしろ、何度も立ち止まり、揺らぎ、悩みながら進んでいる。
でも、それでいい。
壊れやすい自分を抱えながら、それでも「どう生きるか」を考え続ける姿勢は、何よりも尊い。
今日もきっと、あなたは目の前の誰かのために、懸命に動いていたはずだ。
弱さは、ダメじゃない。むしろそれは、あなたが人間である証だ。
どうかそのことを、忘れないでいてほしい。
壊れやすいのに考え続ける、そんな自分を、どうか誇っていい。
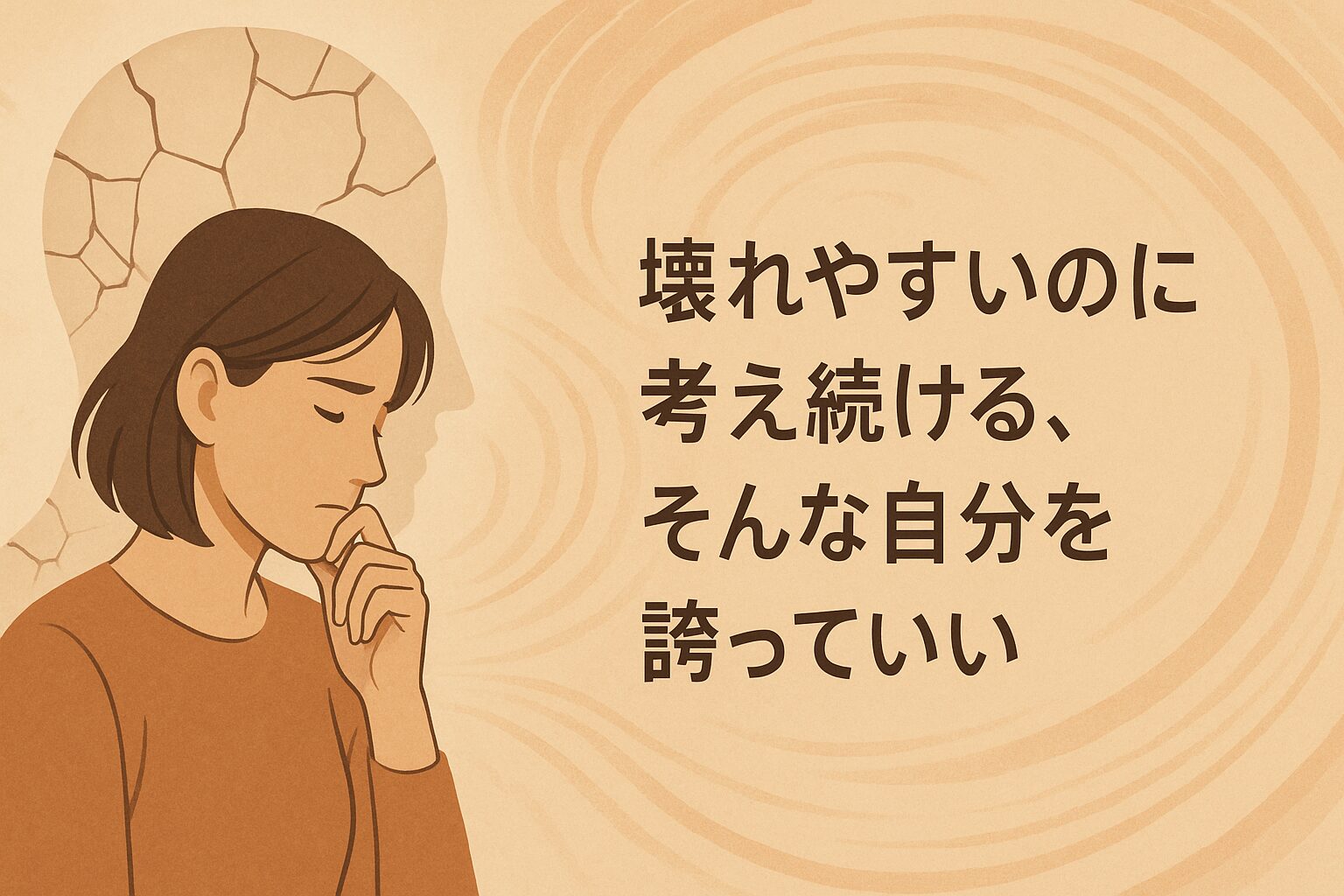


コメント